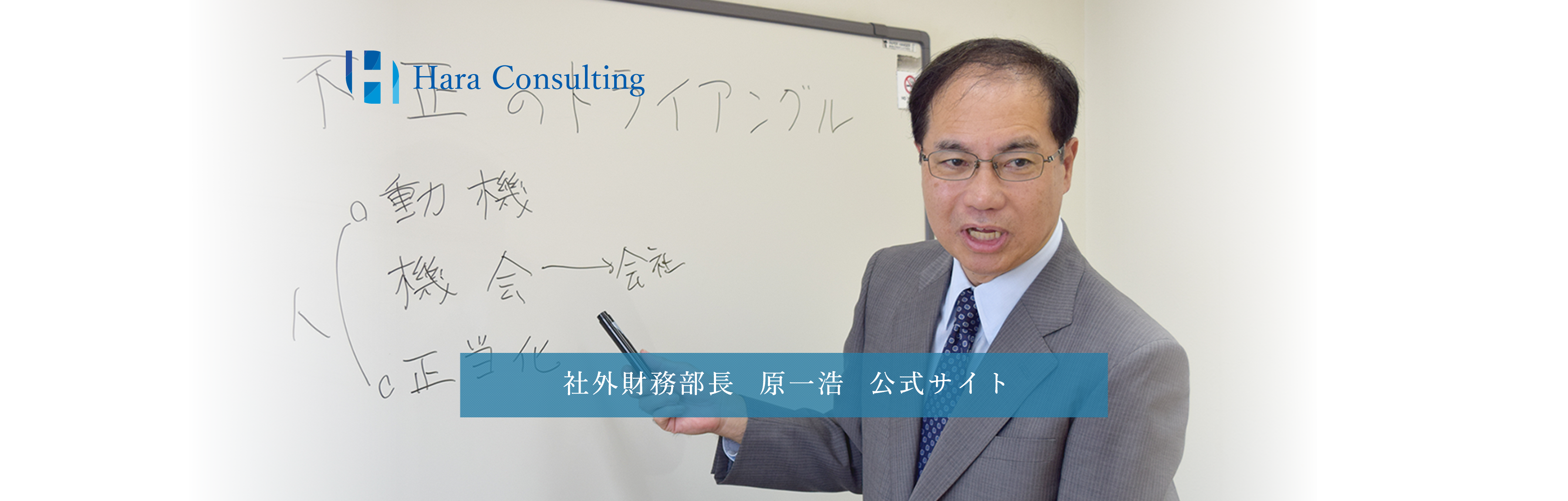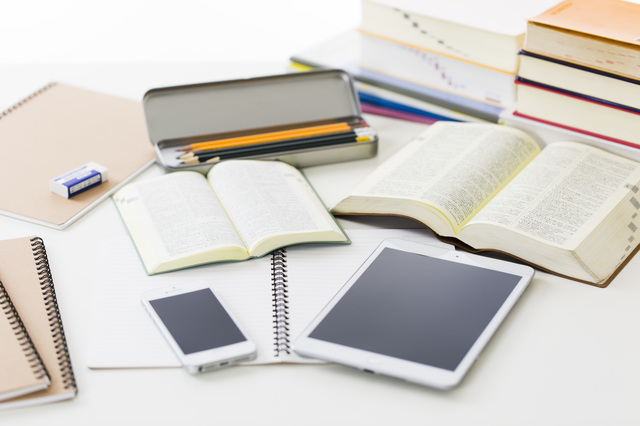事業承継円滑化のために様々な税制措置が取られています。
1.事業承継税制の概要
中小企業・小規模事業者の非上場株式等に係る相続税・贈与税が納税猶予・免除されます。 (法人版事業承継税制)
個人事業者も事業用資産を承継する際に課される相続税・贈与税が納税猶予・免除されま す。(個人版事業承継税制)
- 非上場株式等を相続又は贈与により取得した後継者
- 一定の事業用資産を相続又は贈与により取得した個人事業者
- 特定小規模宅地を相続した個人事業者・後継者
2.非上場株式を相続又は贈与により取得した後継者【法人版事業承継税制】
(1)非上場株式等についての『相続税』の納税猶予・免除制度
後継者(親族外も対象)が、相続又は遺贈により、非上場会社の株式等を先代経営者(被相続人)から取得し、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受け、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等に係る相続税の納税が猶予され、後継者が死亡した場合などには、猶予税額が免除されます。
(2)非上場株式等についての『贈与税』の納税猶予・免除制度
後継者 (親族外も対象 )が、贈与により、非上場会社の株式等を先代経営者から全部又は一定以上取得し、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受け、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等に対応する贈与税の納税が猶予され、後継者が死亡した場合などには、猶予税額が免除されま す。
(3)法人版事業承継税制の特例措置
2018年4月1日から、法人版事業承継税制の特例措置が創設されました。
2018年4月1日から2023年3月31日までの5年以内に経営承継円滑化法に基づく「特例 承継計画」を都道府県知事に提出したうえで、2018年1月1日から2027年12月31日までの 10年間に行われた非上場株式の贈与・相続が対象となります。
従前の措置も一般措置として存在していますが、特例措置については一般措置と比べて以下の点で大きく優遇される内容が拡充されています。
①経営環境変化に対応した減免制度を導入
後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与 ・相続税が納税されていましたが、売却時や廃業時の評価額を基に納税額を再計算することになりました。これにより、承継時の株価を基に計算された納税額との差額が減免されます。
②対象株式数の上限撤廃、猶予割合を100%に拡大
納税猶予の対象になるのは、発行済議決権株式総数の2/3までであり、さらに相続税の納税猶予割合は80%でしたが、対象株式数の上限を撤廃し、納税猶予割合も100%に拡大することになりました。これにより、事業承継時の贈与税・相続税の支払い負担はゼロとなります。
③雇用要件の抜本的見直し
事業承継税制の適用後5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予された税額の全額を納付しなければなりませんでしたが、人手不足の現状を受け、雇用要件を弾力化し、5年平均8割が未達成の場合でも猶予を継続可能といたします(経営悪化等が理由の場合は、認定支援機関の指導助言が必要となります。)。
④対象者の制限の大幅な緩和
一人の先代経営者から一人の後継者に対して贈与・相続される株式のみが対象でしたが、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人まで)への承継も対象となります。
(4)都道府県知事の認定を受けるための主な要件
① 中小企業者であること。
②資産保有型会社等に該当しないこと。
③先代経営者が会社の代表者であったこと。
④先代経営者及びその同族関係者が発行済株式総数の50%超を保有し、かつ、先代経営者がその同族関係者(後継者を除く)の中で筆頭株主であったこと。
⑤後継者及びその同族関係者が発行済株式総数の50%超を保有し、かつ、後継者がその同族関係者の中で筆頭株主であること。
⑥後継者が相続開始の直前に会社の役員であったこと(先代が60歳以上である場合の み)。贈与の場合は、贈与の3年前から引き続き役員に就任していること。 等
2.一定の事業用資産を相続又は贈与により取得した個人事業者【個人版事業承継税制】
2019 年 4 月 1 日から、個人事業者が先代から事業用資産を相続又は贈与により取得した際に課される相続税・贈与税が納税猶予・免除される特例措置が創設されました。
法人版事業承継税制と類似の制度設計となっており、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年以内に経営承継円滑化法に基づく「特例承継計画」を都道府県知事に提出したうえで、2019年1月1日から2028年12月31日までの10年間に行われた一定の事業用資産の贈与・相続が対象となります。
その他、主なポイントは以下のとおりです。
(1)対象となる事業用資産に係る贈与税・相続税を100%猶予することができます。
また、法人版と同様に承継後の経営悪化によって廃業等をした場合は納税が減免されるほか、個人版独自措置として、承継をした個人事業者が一定の身体障害等に該当した場合の免除などが講じられます。
(2)事業用の宅地(400㎡まで)・建物(800㎡まで)、機械・器具備品等の幅広い事業用資産が対象です。
(3)親族外への承継も対象になります。
(4)相続時精算課税制度との併用は可能です。
ただし、個人版事業承継税制と小規模宅地特例(事業用)とは選択適用となります。
3.特定小規模宅地等を相続した個人事業者・中小企業の後継者
(1)小規模宅地等(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)の特例(相続税)
特定事業用宅地等(事業を継続する等の要件があります。)は、400㎡を限度として、相続 税の課税価格に算入すべき価額の80%が減額となる課税の特例を受けることができます。 特定事業用宅地等は、個人版事業承継税制と選択適用になります。
(2)その他、事業承継に際して活用可能な制度
①相続時精算課税制度(贈与税・相続税)
贈与税の申告時に、「相続時精算課税選択届出書」など必要な書類を添付することで、下記のとおり、贈与時に軽減された贈与税を納付して、相続時に相続税で精算する課税制度を選択することができます。
なお、平成30年度税制改正により、事業承継税制の適用を受ける場合には、現行制度に加えて60歳以上の贈与者から、20歳以上の後継者への贈与を相続時精算課税制度の対象とすることとなりました。(贈与者の子や孫でない場合でも適用可能。)
a)(贈与時) 申告を前提に、60歳以上の親又は祖父母から20歳以上の子又は孫への贈与につき、2,5 00万円の非課税枠(限度額まで複数回使用可)があり、これを超える部分については税率一律20%で課税します。
b)(相続時) 贈与時の時価で贈与財産を相続財産と合算して相続税額を計算し、精算します。
②相続により取得した非上場株式を自社に売却した場合の課税の特例(所得税等)
非上場株式を相続した個人が、相続税の申告期限から3年以内に発行会社に相続株式を売却した場合、a)みなし配当課税の特例、b)取得費加算の特例を適用することができます。
a)みなし配当課税(最高55.945%の累進課税)でなく、譲渡所得課税(20.315%の分離課税)が適用されます。
b)また、この場合の非上場株式の譲渡による譲渡所得金額を計算するにあたり、その非上場 株式を相続等により取得したときに課された相続税額のうち、その株式の相続税評価額に 対応する部分の金額を取得費に加算(譲渡所得から控除)することができます。