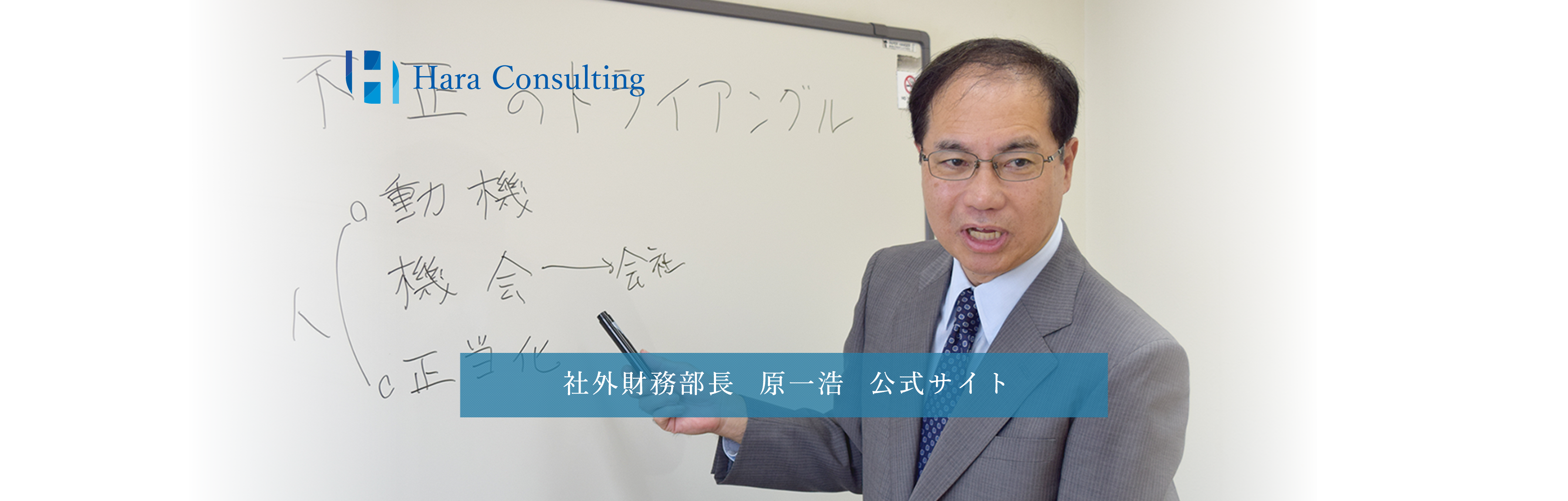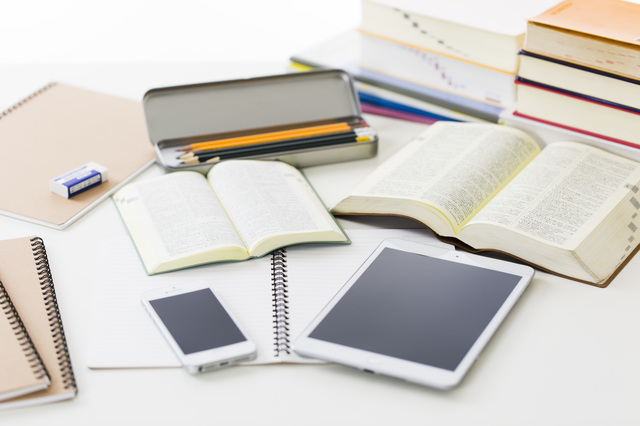1.事業計画分析の意義
事業計画は、将来キャッシュ・フローの前提となるもので、企業価値評価においては、非常に重要なものです。
企業価値を算定するDCF法では、株式価値について将来キャッシュ・フローをもとにして算出するので、事業計画には、損益計画、貸借対照表計画、キャッシュ・フロー計画が必要になります。
事業計画は、ビジネスデュー・デリジェンスと財務デュー・デリジェンスに分けることができます。
事業面は、ビジネスデュー・デリジェンス、計数面は、財務デュー・デリジェンスを行い、事業計画を検討することになります。
2.事業計画の検討
(1)留意事項
事業計画作成の際の前提について、どの範囲まで検討するかを依頼者と合意し、調査範囲を明確にしておく必要があります。
特に、事業計画分析といっても財務諸表の要修正事項のみなのか、キャッシュ・フロー分析も含む事業計画全体の分析かによって、調査結果報告が異なりますので、留意が必要です。
(2)主要な前提
事業計画は、様々な前提を置いて作成されます。
事業計画の前提を把握し理解することは、重要な手続きとなります。
前提の例としては、以下の項目が挙げられます。
①市場の状況
②マーケット・シェア
③売上推移
④仕入れの状況
⑤人員の状況
⑥設備投資計画
⑦マーケティング手法
⑧法規制
(3)事業計画の重要な前提の評価にあたっての留意事項
事業計画の検証は、過去の実績値の検証と将来の計画の前提を結び付けながら将来の事業計画を検討していくことになります。
①過去の事業計画の達成度
過去の事業計画の達成度を確認することは、事業計画の達成可能性を判断する材料になります。
②過去の業績推移
今後の事業計画と過去の業績推移の傾向が整合しているかを確認する必要があります。
過去の事業計画が保守的なものかどうかや、将来の事業計画が楽観的なものかどうかは、過去の業績推移をみることにより、判断することができます。
3.事業計画の全体的評価
主な全体評価手続きは、以下のようになります。
(1)事業計画の作成と会計基準との整合性
会計基準に準拠していない処理がある場合、事業計画において見直すべきか検討する必要があります。
(2)事業計画の作成方法
事業計画の作成プロセスと承認プロセスを確認し、全社的に整合性がとれたものであることを確認しておく必要があります。
(3)損益計画以外の計画との整合性
事業計画には、損益計画、貸借対照表計画、キャッシュ・フロー計画が含まれますので、これらの計画が連動していることを確認する必要があります。
4.損益計画分析
損益計画分析は、事業計画分析の柱となるものです。
(1)売上高分析
事業計画における売上計画は最も重要なものです。
①会社の属する事業や製品等の市場規模等の推移と会社の過去の業績との相関関係の分析
②既存事業の動向と新規事業の実現可能性
③売上単価と数量の前提、返品・値引き等
(2)売上原価分析
①材料費、労務費、経費等の推移、比率分析
②材料単価推移、人員計画、昇給率等
③棚卸資産の評価減
(3)販売費及び一般管理費分析
①売上との連動
②人員計画、設備投資計画との連動
③管理可能費と管理不能費の区別
5.キャッシュ・フロー計画分析
将来のキャッシュ・フローが合理的に算定されているかがポイントとなります。
(1)フリー・キャッシュ・フロー
フリー・キャッシュ・フローは、「税引き後営業利益+減価償却費±運転資本増減-設備投資」となるので、損益計画、設備投資計画等との整合性に留意します。
(2)税金費用
税引き後営業利益を算出するためには、税金費用の算定が重要になります。
税引き前営業利益に実効税率を乗じて税金費用を算定する場合には、一時差異とならない税務と会計の差異がある場合には留意する必要があります。
(3)減価償却費・設備投資額
設備投資計画と減価償却費との整合性を検討します。
(4)運転資本の増減
将来の運転資本の増減を見積もる場合には、フローとストックの整合性がとれているかに留意します。
(5)資金調達計画
営業キャッシュ・フロー、運転資本の増減、設備投資を考慮した資金調達計画になっているかに留意します。
6.貸借対照表計画分析
(1)他の計画との整合性
貸借対照表計画は、売上や仕入れなどの損益計画に債権債務の回転期間を想定して作成します。
また、設備投資計画に基づいた固定資産残高の見積もりも行います。
各種の前提と貸借対照表計画の整合性に留意する必要があります。
(2)純資産額
税金計算や剰余金の処分計画がおろそかになっている場合がありますので、留意する必要があります。
(3)非事業用資産
非事業用資産の処分について、その内容や処分の可能性を検討しておく必要があります。